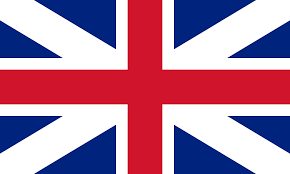本日は新規のお客様がご訪越くださり、ベトナム南部のBen Tre(ベンチェ省)にあるエビ養殖場をご案内いたしました。視察先はホーチミン市内から車で約3時間半、南シナ海に近い沿岸地域に位置しています。ベンチェ省は豊かな自然環境と水資源に恵まれており、エビ養殖の一大拠点として知られています。
世界のエビ市場とベトナムの位置づけ
2022年の統計によると、世界のエビ漁獲量ランキングでは中国(6,853,923トン)、インド(1,438,984トン)に次いで、ベトナムは第3位(1,288,988トン)に位置しています。かつてエビ輸出大国として知られたタイを抜き、ベトナムは今や東南アジアにおける養殖エビの最注目国となっています。背景には、政府による水産業振興政策や、グローバル市場への輸出拡大戦略があり、国内のインフラ整備や養殖技術の高度化も進んでいます。
養殖されているエビの種類とその特性
今回視察した養殖池では、主にブラックタイガー(Penaeus monodon)とバナメイエビ(Litopenaeus vannamei)の2種が育てられています。ブラックタイガーは大型で高値が期待される反面、育成には約120日を要するのに対し、バナメイエビは約90日で出荷可能で、年間に3〜4サイクルの養殖が可能です。現在はバナメイエビが主力となっており、市場のニーズにも柔軟に対応できる体制が整っています。
持続可能な養殖のための工夫
長年同じ池を使い続けると、底にフンや残餌が蓄積し、アンモニアが発生、PH値が不安定になるなどの問題が生じます。これがエビの病気や大量死の原因となり、最悪の場合は池を閉鎖せざるを得ません。そのため、今回訪問した養殖場では水質管理と衛生管理を徹底しており、特に池の内外をビニールシートで囲い、紫外線・外敵(鳥など)の影響や土壌汚染を最小限に抑える設計がなされていました。このような完全被覆型の養殖池は、ベトナム国内でも先進的な例であり、環境に配慮した「持続可能な養殖」のモデルケースとして注目されています。

1回の出荷が終わると全て張り替えます。

池の中の様子。エビが酸欠にならないように手前の風車のような設備を回転させて池の水に空気を送り込みます。
養殖場の規模と輸出体制
視察先の養殖場の総面積は20ヘクタールにも及び、最大で年間300トンの出荷が可能です。収穫されたエビはそのまま冷凍トラックで加工輸出企業に搬送され、サイズ毎に分類された後、アメリカや日本などの高付加価値市場に輸出されます。エビはサイズによって単価が異なり、特に大型サイズは高値で取引されるため、生産者にとっても品質管理のインセンティブとなっています。
養殖工程と稚エビの育成
エビ養殖は、稚エビの投入から始まります。たとえば池のサイズが5,000平米、深さ1.6mの場合、初期には170万匹もの稚エビを投入します。生存率はおおよそ80%とされており、これは他の養殖場と比較しても非常に優秀な数字です。育成の途中段階で各池に分配され、最終的には1kgあたり20匹程度のサイズまで成長します。

稚エビ投入してから27日後のサイズだそうです。

このサイズになると他の池へ放流します。
エサと設備へのこだわり
稚エビ用のエサは非常に高価で、品質にも気を配る必要があります。一方、大人用のエサはコストと量のバランスを見ながら調整されています。視察した養殖場では、主に中国製の飼料を使用しており、消費量の多さから、年末にはサプライヤーから中国旅行に招待されるというエピソードも伺いました。水の管理にも工夫が見られます。池の水は毎日入れ替えられ、別途設けられた貯水槽で海水をろ過し、上澄みだけを池に供給します。このプロセスによって、水質が保たれ、エビの健康が守られています。

稚エビ用のエサ。稚エビ用のエサは大人用よりも高額です。

大人用のエサ。中国製です。
 養殖池は毎日水を入れ替えるので、予め水をためておきます。この際に不純物をろ過し、池には上澄みだけを使用します。水は海水を引っ張っています。
養殖池は毎日水を入れ替えるので、予め水をためておきます。この際に不純物をろ過し、池には上澄みだけを使用します。水は海水を引っ張っています。
日本製商材の導入に向けた展望
今回の視察では、当社が企画している日本製の養殖支援資材の導入可能性について、現場の意見を直接伺うことができました。視察先のオーナー様からは非常に前向きなご反応をいただき、今後は試験導入を含めたモニタリングを進めていくことが決定しました。日本の精密技術や高品質資材は、ベトナムのような成長市場においても差別化要因となると考えられ、当社としても今後の事業展開に向けて大きな一歩となりました。
往復7時間の長距離移動を経ての視察でしたが、非常に有意義な機会となりました。エビ養殖業界は今まさに変革の時を迎えており、持続可能性や高品質への要求が年々高まっています。ベトナムの現場と日本の技術の融合によって、新たな価値が生まれることを信じて、今後も現地との連携を深めてまいります。