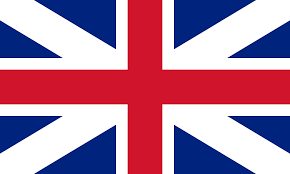本日は、生態系に配慮した水質浄化技術を持つ日本のメーカー様とともに、ホーチミン市の農業ハイテク機構(AHTP)を訪問してきました。今回の訪問の目的は、ベトナムで急成長中のエビ養殖業に対し、日本の持つ環境調和型の水質管理技術がどのように貢献できるかを現地の専門家と議論し、技術連携の第一歩を踏み出すことでした。

ベトナムにおけるエビ養殖と環境問題
ベトナムは世界でも有数のエビ輸出大国です。ブラックタイガーやバナメイといった種が多く生産され、日本をはじめとした多くの国へ輸出されています。しかしその一方で、排水による環境汚染や病気の発生といった課題も深刻です。水質悪化による収穫量の低下や、薬剤への依存は、持続可能な産業発展の妨げになります。そんな中、日本のメーカー様が開発された水質浄化剤は、自然由来の成分を用い、生物に影響を与えずに水質を改善するというユニークな特長を持っています。既に東南アジア諸国の養殖場では、生産効率アップや疾病リスクの低減、排水改善といった成果を上げており、今回はそのベトナム展開を目指した現地訪問となりました。
AHTPとは? 農業×テクノロジーの融合モデル
訪問先の「ホーチミン市農業ハイテク機構(AHTP)」は、2004年にホーチミン市人民委員会の主導で設立された、ベトナム農業の頭脳と心臓ともいえる施設です。敷地は88ヘクタールにも及び、研究・試験農場、温室、水耕栽培設備、種苗センター、加工施設、技術展示ホールなどが集結し、農業の6次産業化(生産・加工・流通・販売・教育・普及)を一貫して担える環境が整っています。ここには民間企業や大学も積極的に関与しており、スマート農業や都市農業の実証モデルとしても知られています。AHTPの姿は、日本で言えば「農研機構」「JIRCAS」「県の試験場」「農業大学」「産業支援センター」をすべて一か所にまとめたようなイメージで、ベトナム農業の未来を担っています。
エビ養殖場も運営
AHTPは2015年頃からホーチミン市カンゾー地区で独自のエビ養殖場も展開しています。約89.7ヘクタールもの広さを持ち、この場所ではスマート技術を駆使した42の養殖ユニットが整備され、実証研究と商業生産が両立されています。以下のような技術群を持ち合わせています:
- 閉鎖循環式の水再利用(RAS)
- バイオフロックによる自然浄化
- IoTを活用した水質センサーと自動給餌
- 遠隔監視カメラ+AIによる異常検知
- VietGAP/GlobalGAPに準拠した運営管理
これらを活用し、環境負荷を最小限に抑えつつ、高品質なエビの安定供給を可能にしているそうです。
実際の技術連携の可能性
打ち合わせでは、「水質管理」がいかにエビの成長に直結するかという話題になりました。AHTPの技術者の方々も、浄化剤の導入によって酸素不足やアンモニア蓄積などのリスクをどう低減できるかに大きな関心を寄せていました。さらに、水質の安定化は、
- 餌の効率的な利用(=コスト削減)
- 病原菌の蔓延防止(=薬剤の使用削減)
- 排水の無害化(=地域環境保護)
にもつながるため、持続可能な養殖業への道筋として有望だとお考えいただけ、今後は試験の実施や技術研修、セミナーの展開などを検討していくこととなりました。
ベトナム農業に広がる日本の技術
今回の訪問は、単なる商談というよりも、「日越の農業をより強固なものにする未来への第一歩」と感じられるものでした。ベトナムでは、AHTPのような先進的な研究施設が整い、かつ現場の課題に対して真摯に取り組もうとされています。そこに、日本の技術が加わることで、新しい農業のモデルが生まれるのではと期待しています。
最後に
養殖エビの世界市場は年々拡大していますが、ただ量を増やすのではなく、「品質と環境の両立」が今後の鍵になると考えられています。AHTPの取り組み、そしてそれを支えるような日本の技術との融合が、アジア全体の農業・水産業の変革をもたらす可能性を秘めています。私たちもこの取り組みを通じて、「ベトナムの現場に根差した、本当に役立つ技術支援」を目指し、今後も継続的にサポートしていきたいと考えています。
関連記事はこちら